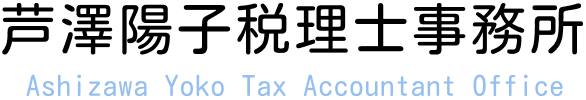配偶者控除で相続税がゼロに?知って得するメリットと注意点
相続税の負担を大きく減らせる制度のひとつに「配偶者の税額軽減」があります。
配偶者が相続人となる場合、一定の金額までは相続税がかからないという特例です。
今回は配偶者控除のメリットや適用の際の注意点について解説します。
配偶者の税額軽減とは
配偶者の税額軽減とは、配偶者が相続によって取得した財産について、次の金額までは相続税が課税されない制度です。
1億6000万円または法定相続分のいずれか多い金額まで非課税
この制度によって、配偶者がすべての遺産を相続した場合でも、相続税の申告を行えば課税されないことがあります。
制度の趣旨は、残された配偶者の生活を保障するためであり、実際に多くのケースでこの特例が利用されています。
配偶者控除を受けるメリット
この制度には、いくつかのメリットがあります。
まず、非課税枠が大きいため、多くのケースで相続税の支払いが不要になる可能性があります。
次に、生前対策をしていない家庭でも、一定の節税効果が期待できます。
さらに、配偶者に相続させる割合を大きくすることで、他の相続人への影響を最小限にとどめる選択が可能になります。
実務上も、申告をきちんと行うことで、税務署から否認されることは少ないとされています。
申告が必要な点に注意
配偶者の税額軽減は、自動的に適用される制度ではありません。
たとえ相続税がゼロになる場合でも、適用を受けるためには相続税の申告書を提出する必要があります。
申告期限は、相続が発生した日の翌日から10か月以内です。
申告を行わずに期限を過ぎてしまうと、軽減措置が受けられず、多額の税負担が発生する可能性もあります。
また、配偶者が取得する財産の評価額が妥当かどうかは、相続税全体の算出に影響するため、不動産や非上場株式などの評価は慎重に行う必要があります。
将来の二次相続にも注意が必要
配偶者控除によって相続税が発生しなかったとしても、その財産は配偶者の死亡時に、再び相続の対象となります。 これが「二次相続」です。
一次相続の際に配偶者が多くの財産を取得していると、二次相続の際に基礎控除を超える可能性が高くなり、相続税の負担が増えることがあります。
そのため、配偶者控除を使う際には、一次相続だけでなく、二次相続の影響も見据えた設計が求められます。
生前から財産の分割や贈与、信託なども視野に入れた対策を検討することが重要です。
まとめ
配偶者の税額軽減制度は、相続税の負担を大きく減らせる有効な手段です。
ただし、非課税になる場合でも申告が必要であり、適用には一定の要件を満たす必要があります。
さらに、将来の二次相続を見据えた対応を怠ると、かえって相続税負担が重くなる可能性もあります。
制度の内容や適用条件を誤ることなく活用するためには、税理士の専門的なサポートを受けることが重要です。
相続に関する不安や疑問がある場合は、早めに税理士に相談し、最適な相続設計を検討することをおすすめします。