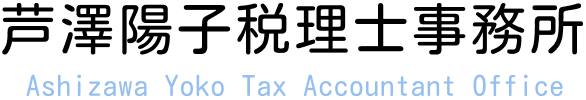相続税の申告が必要かどうか迷ったら|ケース別の判断ポイントと期限
相続が発生したとき、相続税の申告が必要かどうかは状況によって異なります。
必ずしもすべての相続において申告が必要なわけではなく、条件次第では申告自体が不要な場合もあります。
今回は、申告が必要となる主なケースや判断の基準、申告期限について考えていきたいと思います。
相続税の申告が必要な条件
相続税の申告が必要となるのは、遺産の総額が「基礎控除額」を超える場合です。
基礎控除額は、次の計算式によって決まります。
基礎控除額=3000万円 + (600万円 × 法定相続人の数)
たとえば、法定相続人が2人いる場合、基礎控除額は4200万円となります。
遺産の総額が4200万円を超えると、相続税の申告が必要です。
なお、遺産の総額には以下のような財産も含まれます。
- 預貯金や有価証券、不動産などの資産
- 死亡保険金や死亡退職金(一定額を超える部分)
- 相続開始前3年以内の贈与財産
こうした要素を合算し、基礎控除を超えるかどうかを判断します。
申告不要なケース
遺産総額が基礎控除額以下の場合、相続税の申告は不要です。
また、配偶者が相続する財産については、「配偶者の税額軽減」という特例があり、1億6000万円または法定相続分までは課税されません。
この特例を使うことで、配偶者がすべて相続する場合は申告が不要になるケースもあります。
ただし、非課税であっても次のような特例を使う場合には申告が必要です。
- 配偶者の税額軽減
- 小規模宅地等の特例
これらを適用するには、税務署への申告を通じて手続きを行う必要があります。
申告期限と延滞に注意すべき点
相続税の申告期限は、「被相続人が亡くなった日の翌日から10か月以内」です。
この期限までに、所轄の税務署へ申告書の提出と納税を済ませる必要があります。
期限を過ぎてしまうと、延滞税や加算税が発生する可能性があります。
税務署からの指摘があった場合には、無申告加算税として最大20%が加算されることもあるため注意が必要です。
期限までに評価や分割が終わらない場合でも、まずは期限内に申告だけ行い、後日修正申告や更正の請求をすることが可能です。
そのためにも早めに準備を始めることが大切です。
判断が難しいときの対応
遺産の評価や控除の適用条件によっては、申告の要否が判断しにくいこともあります。
不動産の評価や保険金の扱い、非上場株式の評価など、専門的な知識を要する項目も多く含まれています。
不安がある場合には、早めに税理士などの専門家に相談することが重要です。
まとめ
相続税の申告が必要かどうかは、遺産の内容や金額、相続人の数など複数の要素によって変わります。
基礎控除の範囲内に収まっていれば申告不要な場合もありますが、特例を利用する際には申告が必要となるケースもあるため、注意が必要です。
判断が難しい場合は、税理士に相談することで適切な対応が可能になります。