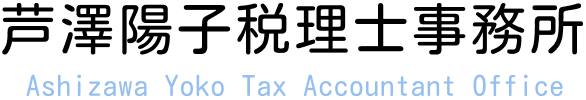土地・建物の相続税評価と計算方法を税理士が解説
土地や建物を相続した場合、相続税の計算にあたって評価方法が重要なポイントとなります。
現金や預貯金とは異なり、不動産は評価方法によって大きく課税額が変動するため、正しい知識が必要です。
今回は、土地と建物それぞれの評価の考え方と、計算の基本的な流れについて紹介します。
土地の評価方法
相続税において土地の評価は、主に「路線価方式」または「倍率方式」により行います。
どちらを使うかは、その土地の所在エリアや状況によって異なります。
路線価方式は、国税庁が毎年公表する「路線価」に土地の面積を掛けて評価額を算出します。
これは都市部や主要な住宅地でよく用いられます。
一方、倍率方式は固定資産税評価額に一定の倍率を掛けて評価する方法で、地方や路線価の定められていない地域に使われます。
土地の形状や接道状況によっては、評価額が補正されることもあります。
不整形地や無道路地などは評価が下がる可能性があるため、個別の確認が必要です。
建物の評価方法
建物の評価は、原則として固定資産税評価額を用います。
これは市区町村が課税の基準とする評価額で、実勢価格とは異なります。
たとえば、築年数が古い建物は減価されており、評価額も低くなる傾向があります。
ただし、リフォームや増築をしている場合は、実態と評価額が乖離しているケースもあるため注意が必要です。
なお、賃貸物件など収益を生む建物の場合は、借家権割合や賃貸割合を反映させた評価が必要です。
このような特殊なケースは、専門的な知識を要するため、個別対応が求められます。
評価額に影響を与える特例
土地と建物の評価においては、一定の条件を満たすことで適用できる特例があります。
代表的なものに「小規模宅地等の特例」があります。
これは、被相続人が居住していた土地などについて、一定面積まで評価額を大幅に減額できる制度です。
たとえば、配偶者や同居親族が自宅を相続した場合、330平方メートルまでの居住用宅地の評価額を80%減額できます。
適用には厳密な条件があるため、事前の確認が欠かせません。
相続税の計算における不動産評価の重要性
不動産の評価は、相続税額の算定に直結します。
評価額が高すぎれば過大な納税につながり、低すぎれば税務調査で否認されるリスクが生じます。
特に土地の形状や利用状況に応じた補正、建物の用途別評価などは専門的な判断が必要であり、誤ると後のトラブルにつながる可能性があります。
また、申告期限である10か月以内に適切な評価を行うためには、早めの対応が求められます。
まとめ
土地や建物の相続税評価は、制度や実務に対する正確な理解が求められる分野です。
評価の方法を誤ると税額に大きな影響を与える可能性があるため、適切な判断が欠かせません。
特例の適用や不動産の個別事情に応じた調整なども含め、税理士に相談しながら進めることで、適正かつ安心な申告と相続対策が可能になります。