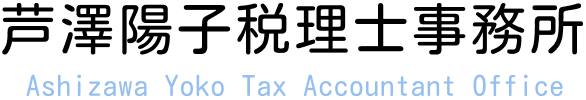相続税対策に「生前贈与」は有効?メリットと注意点について解説
将来の相続税対策として、生前贈与を活用する動きが増えています。
生前のうちに財産を移転することで、相続時の負担を減らすことが期待されますが、制度の活用には慎重な判断が求められます。
今回は、生前贈与のメリットと注意点について整理します。
生前贈与の主なメリット
生前贈与には、相続税の軽減や円滑な資産移転といった利点があります。
最大の特徴は、相続開始前に財産を移すことで、相続税の課税対象となる財産を減らせる点です。
贈与税の非課税枠である「年間110万円以内」であれば、申告も不要で、毎年少しずつ資産を移す「暦年贈与」が可能です。
また、教育資金や結婚・子育て資金を目的とした贈与には、一定の非課税制度が設けられており、適用を受ければさらに大きな金額の非課税贈与が可能となります。
さらに、財産の配分を生前に自ら決めることで、遺産分割に関するトラブルの予防にもつながります。
注意すべきデメリット
一方で、生前贈与には注意すべき点もあります。
まず、贈与税の負担です。
非課税枠を超えた部分には贈与税が課税され、その税率は相続税よりも高くなる場合があります。
また、相続開始前3年以内の贈与は、相続財産に加算される「持ち戻し」の対象となるため、直前の贈与では節税効果が薄れる可能性があります。
受贈者が未成年や無収入の場合、贈与によって取得した財産の管理が課題になることもあります。
不動産を贈与する場合は、登録免許税や不動産取得税、名義変更の手続きなども必要となり、コストと手間がかかります。
生前贈与がきっかけで家族間の資産格差が可視化され、かえって関係が悪化する事例も見受けられます。
制度選択と計画性の重要性
生前贈与には複数の制度が存在しており、目的や贈与額、受贈者の状況に応じて選択することが求められます。
暦年課税制度と相続時精算課税制度のどちらを選ぶかによって、税額計算の方法や将来の相続への影響が異なります。
特に相続時精算課税制度を一度選択すると、以後は取り消すことができないため、制度の内容や将来の資産状況を見据えたうえで判断する必要があります。
贈与の目的が明確であり、かつ中長期的な資産形成や相続対策の一環として実施することが重要です。
場当たり的な贈与では、想定外の税負担や家族間のトラブルを招く可能性もあります。
まとめ
生前贈与は、相続税の負担軽減や遺産分割の円滑化など、多くの利点がある手段です。
しかし、税制の仕組みや制度選択を誤ると、期待する効果が得られない場合もあります。
贈与額、時期、対象者の選定、そして各制度の適用条件を総合的に検討するためには、税理士の支援が有効です。
将来のトラブルを防ぎ、安心して資産を引き継ぐためにも、早めの相談を検討してみてください。